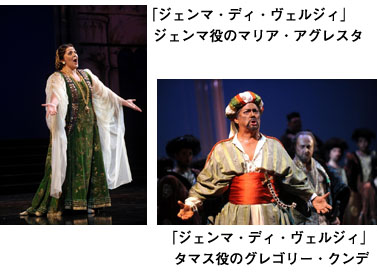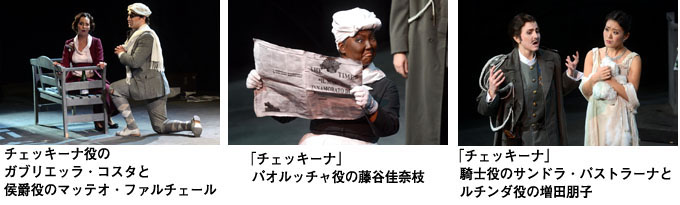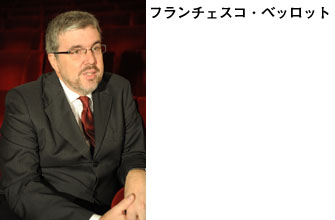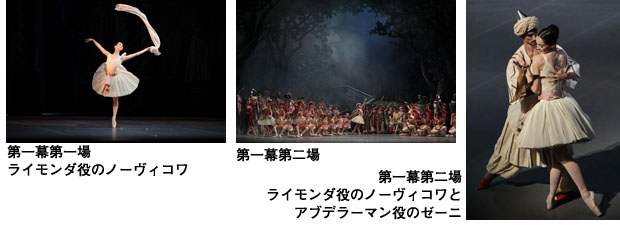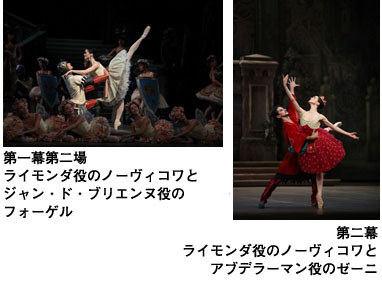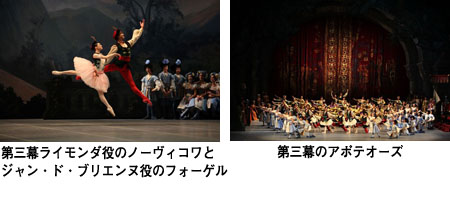|
OPERA NEWS (ベルガモ発)
Bergamo Music Festival 2011・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・by Mika Inouchi ベルガモ音楽祭2011年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井内美香 Photo: Gianfranco Rota |
|
|
|
BALLET Review (ミラノ発)
Raymonda - Teatro alla Scala・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・by Mika Inouchi スカラ座バレエ「ライモンダ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井内美香 Photo: Brescia e Amisano |
|
|