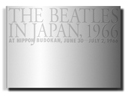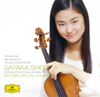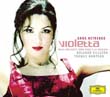![]()
| Popular ALBUM Review | |
| 「イン・マイ・マインド/ヘザー・ヘッドリー」(BMG JAPAN/SVCP-21474) ヘザー・ヘッドリーはカリブ海の島トリニダッド・トバゴ生まれだが、15歳で渡米。大学で音楽を専攻。ミュージカル『ライオン・キング』の重要な役でデビュー後、『アイーダ』で主演。トニー賞を獲得している。ヒップ・ホップやリズム主体のR&Bシーンで、彼女はオーソドックスなヴォーカルを聞かせる。まだアニタ・ベイカーほどコクはないが、瑞々しさがいい。この第2作はタイトル曲「イン・マイ・マインド」が特に情感豊かで酔わせる。ヒップ・ホップは歌うよう。60年代風R&Bもあるが、ほとんどがバラード。彼女のバラ-ドはメリハリがはっきりしていて、熱唱より抑制の効いた演唱は大学時代とステージで鍛えたものと思われる。締めくくりの「チェンジ」はスケールが大きく見事。(鈴木 道子) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「ステイ・アンド・ラヴ・ミー・オール・サマー/ブライアン・ハイランド」 (ユニバーサル ミュージック/UICY-93081) ブライアン・ハイランドといえば日本では「ビキニ・スタイルのお嬢さん」や「ベビー・フェイス」「シールド・ウィズ・ア・キッス(涙の口づけ)」といったティーンエイジ・アイドル時代のヒット曲でしか一般的には認知されておりませんが、リアルタイムではないちょっと若い世代のファンはそれ以降の1960年代後期~1970年代初期にかけての作品の数々に目を向けています。いわゆる‘ソフト・ロック’な趣というやつですね。その内の1枚がこの1969年のアルバム。DOTレコードからの2作目ですが、小ヒット(全米82位)に終わったもののタイトル曲の甘酸っぱさを湛えた夢見心地な魅力は逸品(昔っから大好きでした♪)。‘ヴォイス・オブ・サマー’とも言われるハイランドですが、この曲などはまさにそんな彼の後期名作の一つ(作者のアル・カシャ&ジョエル・ハーシュボーンは後に映画「ポセイドン・アドヴェンチャー」の主題歌「ザ・モーニング・アフター」でアカデミー歌曲賞を獲得する名コンビ)。他にもジミー・クラントン、クローヴァーズ、ペパーミント・トロリー・カンパニーやジョニー・ティロットソンのヒット・カヴァーなど興味深い内容ですが、目に留めていただきたいのがこのジャケット♪そう、この復刻盤はヴィジュアル・ブック「Beautiful Covers/ジャケガイノススメ」(毎日コミュニケーションズ:5月下旬刊行予定)と連動したレコード3社合同企画(5/24と6/21に計18枚が紙ジャケットで!)の一環で出されるもので、そんな観点からも楽しめる1枚です。(上柴 とおる) |
|
| Popular ALBUM Review | |
|
「ファンタズマ vol.II /林正子」(ソニー・ミュージック/SICC300) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「サンダーバード/カサンドラ・ウィルソン」(東芝EMI/TOCP-67885) カサンドラは女性ジャズ歌手の最高峰だが、この2年ぶりの新作は、インディアンの守り神ともいわれている「サンダーバード」をテーマに民謡「レッド・リヴァー・ヴァレー」「ボー・トゥ・メキシコ」などを歌い、アメリカ人のルーツにアプローチしているのが注目される。ルーツに立脚した上でこれからの音楽を創造しようとしていて興味ぶかい。ギター・サウンドとロック・ビートなどサウンドも多彩だ。(岩浪 洋三) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「枯葉/レディ・キム」(ヴィレッジ・ミュージック/VRCL18832) アメリカ出身の黒人ジャズ・シンガー、レディ・キムの3作目。1~2作目ですでにしっかりとした歌唱と雰囲気を醸し出していたが、この3作目ではさらに磨きがかかっている。表題曲「枯葉」のほか、「縁は異なもの(恋は異なもの)」「コロコヴァード」 などおなじみの曲がしっとりと歌われる。ジャズ・ヴォーカルをちょっと聴きたいような夜にお勧めの一作である。(吉岡 正晴) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「スウィング・スウィング・スウィング/マンハッタン・ジャズ・オーケストラ」 (ビデオ・アーツ・ミュージック/VACM1284) 7月の来日公演が決まったMJOの最新録音で、最近人気のスイング・ナンバーを中心にしている。チューバやフレンチ・ホーンも加えたこのバンドは、今アメリカのビッグ・バンド中、もっともダイナミックでカラフルでエキサイティングだ。マシューズの作・編曲も秀逸で、ビッグ・バンドの楽しさを満喫した。ル・ソロフ、ランディ・ブレッカー、ライアン・カイザー(tp)ジム・ピュー(tb)クリス・ハンター(as)とソロイスが揃っているのも魅力だ。新編曲の「A列車で行こう」「マンテカ」「ジャン・ン・アット・ウッドサイド」とマシューズ作のアルバム・タイトル曲が聴きものだ。(岩浪 洋三) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「処女航海/オースティン・ペラルタ」(ヴィレッジ・ミュージック/VRCL18831) ローリング・ストーンズ日本公演中にバックを務めるティム・リース(サックス奏者、キーボードもこなす)から、とにかく聴きなさい、若いけど素晴らしいジャズ・ピアニストだと推奨されたのがオースティン・ペラルタ。若いというので20代だと思っていたら、何と15歳!1990年10月25日生まれなのだ。6歳からクラシック・ピアノを始め、10歳からはジャズも習得。本作がデビュー作、ピアノ・トリオでの録音でベースがロン・カーター、ドラムスはビリー・キルソン。マッコイ・ターナー、ハービー・ハンコック、ジョン・コルトレーンのナンバーなどを次々に見事に披露する。その説得力ある演奏ぶりはまさに年齢を忘れさせる。9曲中「N.Q.E(Naguib Qormah Effendi)」「バラキーティ」の2曲はオリジナル作品。3~4月にかけてのライヴ・イン・ジャパンも素晴らしかったと聞く。2作目、3作目でのより大きな飛躍が楽しみだ。(Mike M. Koshitani) |
|
| Popular ALBUM Review | |
| 「アモール/中谷泰子」(Lyra Records/LRJZ1014) 中谷泰子は、関西を中心に東京でも活躍しているピアノの弾き語りシンガー。彼女の5作目は、タイトル曲や「アンダルシア」「アマポーラ」「キエン・セラ」等のラテン・ナンバーを主体にギターや、曲によってヴァイオリンも入るグループで歌う手作りといった感じの楽しいアルバム。クラシックで鍛えた伸びやで明るく美しい声が魅力。ヴァイオリンをフルに活用してチャレンジするチック・コリアの「スペイン」が印象的だ。(高田 敬三) |
|
| Popular CONCERT Review | |
  Photo:轟 美津子 |
「ザ・ローリング・ストーンズ ア・ビガー・バン・ツアー」 3月22日 東京ドーム ストーンズの東京ドーム(3/22&24)、札幌ドーム(3/29)、さいたまスーパーアリーナ(4/2)、ナゴヤドーム(4/5)全5公演を堪能した。いずれも素晴らしいの一言に尽きる内容だった。世界最強ロックンロールバンドとしての実力とパワーをみせつけたそのコンサート、1960年代からのファンから若い層まで世代を超えた観客がエキサイトしたのだ。まさにロックの歴史、でもそれだけではない、彼らは現在も躍進を続けている。昨年発表した新作からのナンバーも実にもちろんセットリストに加える。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ロニー・ウッド、彼らの止まることを知らないエネルギーは多くの人々を感動させる。昨年夏からスタートしたア・ビガー・バン・ツアーは予定を延長して今年12月まで続くということだ。(Mike M. Koshitani) |
| Popular CONCERT Review | |
 |
「サラ・ガザレク」 COTTON CLUB 3月24日 まだ、高校生だった2000年にNYのリンカーン・センターで行われた「エッセンシャリー・エリントン」のコンテストでエラ・フィッツジェラルド・ヴォーカル賞に輝き、その後、ジョン・コルトレーン・メモリアル・スカラーシップ、ダウンビート学生音楽賞等などを取り2004年と5年にはカーリン・アリソン、ダイアン・シュアー、オレタ・アダムスとシンガー4人によるコンコード・ジャズ・フェステイバルのツアーを行ってレコード・デヴュー以前からおおいに騒がれていた新進ジャズ・ヴォーカリスト、サラ・ガザレクのコンサートが「コットン・クラブ」で行われた。日本盤レコードが発売前なので、客の入りは今ひとつだったが、元気よく伴奏のトリオと舞台に上がった彼女は、「トゥ・ダーン・ホット」をスインギーに歌い、続いてピアニストのジョシュ・ネルソンが書いた初アルバムのタイトル曲「ユアーズ」をしっとりと歌った。そして母がよく歌って聞かせてくれたという「ユア・マイ・サンシャイン」を観客のフィンガー・スナッピンを誘ってリズミカルに歌うといった調子で24歳とは思えない素晴らしいステージ運びで12曲をオーソドックスなスタイルで溌剌と歌った。シアトル出身のバンドの3人も若くクリーンでフレッシュな印象を与えた。彼女の師事したティアニー・サットンの影響もあるのか、歌手と伴奏者というものでなく、バンドと一緒になって歌を作って行くといった面も見られた。彼女は、さわやかな感じの美形で、ストゥールに座ってスローなテンポで珍しいヴァースをつけて歌ったエリントンの「アイ・ガット・イット・バッド」の時には、客席の女性から思わず「可愛い」というつぶやきが出た。珍しいヴァースは、彼女の大好きなエラ・フィッツジェラルドのレコードから教わったのだろう。ベース奏者との男女関係を歌った告白的な彼女のオリジナル、「ユー・ガット・バイ」もなかなか印象的な歌だった。アンコールは、フランク・レッサーの「ネヴァー・ウイル・アイ・マリー」で締めた。前週出演したロバータ・ガンバリーニといい、「コットン・クラブ」は、本当に良い歌手を呼んでくれる。この二人の名前は、これからもジャズ・ヴォーカル界でしばしば聞くことになる様な気がする。(高田 敬三) |
| Popular BOOK Review | |
| 写真集「ビートルズ イン ジャパン1966」(アスコム) 来日40周年企画として出版された写真家ロバート・ウィティカーによる1966年のビートルズ来日時の写真集です。ウィティカーは、あのブッチャー・カバーと呼ばれるビートルズの幻のアルバムジャケットを撮影した人としても有名。羽田空港に着陸する前の飛行機内から、ステージ写真、ホテルの部屋、ホテルから武道館までの車窓から見た風景、バックステージまで、126点ほどを収録。本邦初公開の写真も多く、貴重な日本滞在の記録となっている。6000部の限定発売で限定番号付、さらにステージ写真のオリジナル・プリント付。(広田 寛治) (C)Photographs:Getty Images/Robert Whitaker |
|
| Popular INFORMATION | |
 |
「2006 Junko Moriya Orchestra At Sweet Basil/2005年度ミュージック・ペンクラブ音楽賞受賞記念ライヴ!」 恒例の守屋純子オーケストラ・リサイタルが、一昨年、昨年に引き続き六本木メSweet Basilモで行われる。昨年守屋純子は日本人初の栄誉となる、2005年度セロニアス・モンク・コンペティション作曲部門でグランプリを獲得。この賞はセロニアス・モンク・インスティチュート・オブ・ジャズが1987年より開催し多くの優秀なジャズ・アーティストを世に輩出して世界的な権威を誇る「セロニアス・モンク・インターナショナル・ジャズ・コンペティション」に併設され、1993年から毎年行われているジャズの作曲家に与えられる。 そしてアルバム「Points Of Departure」が2005年度ミュージック・ペンクラブ音楽賞も受賞。今回は日米の賞のダブル受賞を記念したライヴとなる。 <守屋 純子オーケストラ> リズム:守屋純子(P,Arr)、納浩一(B)、大坂昌彦(DRS) サックス:近藤和彦(AS)、緑川英徳(AS)、小池修(TS)、Andy Wulf(TS)、宮本大路(BS) トロンボ-ン:中路英明、片岡雄三、佐藤春樹、山城純子(B-TB) トランペット:エリック・ミヤシロ、木幡光邦、奥村晶、高瀬龍一 日時:2006年5月17日(水) 時間:6:00pm開場 8:00pm開演(入れ替えなし・座席は先着順となります。) 場所:六本木メSweet Basilモ チケット:税込み5000円 予約・お問い合わせ tel:03-5474-0139(月曜-土曜 11.00am-8.00pm) HP "http://stb139.co.jp" ローソンチケット tel:0570-00-0403 |
| Classic ALBUM Review | |
| 「ピーター・マクスウェル・デーヴィス:ナクソス四重奏曲第5番、第6番/マッジーニ四重奏団」(アイヴィ〈ナクソス〉/8.557398) マクスウェル・デーヴィスは1934年生まれ、貴族の称号を持つイギリスの作曲家兼指揮者である。彼は現在ナクソス・レーベルから5年間掛けて10曲の「ナクソス・シリーズ」と呼ばれる弦楽四重奏曲の作曲を委託され、このアルバムはその3枚目に当るものである。第5番は緩徐楽章のみの2楽章構成の曲だが、第6番は多様な6楽章からなる。全体にそれほど斬新な手法を用いてはおらず、聴きやすい。特に第6番の第5楽章(In die Nativitatis)の神秘的な音の流れが不思議な効果を上げている。演奏しているマッジーニ・クヮルテットは、16世紀の有名なヴァイオリン制作者の名前を持つ1988年に組織されたイギリスの団体で、特にイギリスの現代作曲家の作品を得意としている。(廣兼 正明) |
|
| Classic ALBUM Review | |
| 「ペーテル・ヤブロンスキー来日記念」(ユニバーサル ミュージック) チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番、グリーグ ピアノ協奏曲(UCCD-3496) チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番、 ピアノ協奏曲第3番(UCCD-3497) ラフマニノフ:パガニ―二の主題による狂詩曲、その他(UCCD-3498) ラフマニノフ ピアノ・ソナタ第2番、その他(UCCD-3499) N響をはじめ、日本のオーケストラと共演も多く、各地でコンサート活動を活発に行っているスウェーデンのピアニスト、ペーテル・ヤブロンスキー。ヤブロンスキーの特徴は、粒の揃った美しい音と、率直な、もの柔らかい若さに裏打ちされた流動感が表現の主要な支えとなっており、聴き手を快い興奮へと導く。彼のリサイタルを聴いた人ならば誰しもその事を感じたであろう。チャイコフスキーとグリーグのピアノ協奏曲でのヤブロンスキーは絶妙なニュアンスに彩られる繊細さと、豪快な力感との両極点の面を自由自在にしかも適切に弾き分けてゆく。聴きなれたこれら両曲をまことに瑞々しいものとして息づかせる。特にチャイコフスキーでは第2楽章が聴きどころで、弱音の美しさを生かし微妙なピアニズムによって清澄な叙情をねらう。ヤブロンスキーの稀な能力を示す一例である。日本にも多くのファンを持ったスイスの指揮者、ペータ・マークもピアノを美しくひきたてており、オーケストラとピアノがしっかりと融けあっている。 チャイコフスキーのピアノ協奏曲第2,第3番はコンサートでめったに演奏されない曲だが、このCDの解説を記した伊藤よし子氏も述べているように「チャイコフスキーにはこんな曲があるんだよ。敬遠せずに聴いてよ。きっとチャイコフスキーの新たな面を知って、より世界が広がるからさ」とでもヤブロンスキーが言っているように、聴き手の心にストレートに入ってくる。特にピアノ協奏曲第2番の第2楽章は美しく、一度聴いたら忘れる事ができないと思う。ピアノに託されたロマンチックな基本主題とヴァイオリンとチェロのソロによる2重奏が甘く優美な美しさを見せる。 パガニーニの狂詩曲は、各変相の生かし方が巧みで、蒸留水にも似た純度の高い表現。ルトスワフスキーのパガニーニの主題による変奏曲は、色彩的なオーケストレーションと華やかなピアノのテクニックが盛り込まれた魅力的な作品だが、ここでのヤブロンスキーは、その内容を充分な説得力をもってよく弾きあらわしており、陰影が実にはっきりしている。 ロシアの作曲家によるソナタは、抜群のリズム感で、フォルテから微妙なピアニッシモまで、つくり出す音は多様であり多彩。スクリャービンのピアノ・ソナタは洗練された演奏であり音色の変化を巧みに生かしている。ヤブロンスキーはまさに、21世紀の演奏を予感させるピアニストである。(藤村 貴彦) |
|
| Classic ALBUM Review | |
| 「ためらいのタンゴ - タンゴ・コレクション1890-2005/高橋アキ(P)」 (カメラータ・トウキョウ/CMCD-28105) タンゴは、19世紀末にブエノスアイレスで生まれた混血音楽。新しい素材を求めて模索する現代音楽の作曲家たちも、タンゴのスタイル、イデオムを使って多彩な作品を書いている。本盤は19世紀末のアルベニスの曲に始まり、20世紀アメリカの作品、日本の作曲家の作品、ピアソラの曲、少し時代を遡って20世紀前半にフランスで書かれた作品まで、18作曲家、20曲が収録されている。その歴史が見てとれるとともに、21世紀のタンゴの息吹を感じさせる「タンゴ作品集」である。短い曲ばかりだが、各作品の個性が美しくきらめいている。実に楽しいアルバム。(横堀 朱美) |
|
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「ラヴェル:《ラ・ヴァルス》?、ビゼー:交響曲ハ長調《アルルの女》組曲第1番、第2番?/ジャン・マルティノン指揮 シカゴ交響楽団?、ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団?」(BMG JAPAN/TWCL-3012) マルティノンのラ・ヴァルスは、デリケートなニュアンスにあふれ、香気の高い華麗な効果をよく出した演奏であり、日本未発売及び世界初CD化。各パートの一糸乱れぬ積み重なりと楽器のバランスの均衡の見事さでこの曲を一気に聴かせてしまう。オーマンディのビゼーの交響曲も今回初の一般発売である。オーマンディはレパートリーの広い指揮者であったが、すべてが中庸を得た表現であり、今回のビゼーもテンポ、ダイナミック、すべて過激な所はない。フィラデルフィア管弦楽団の管は実に美しく、「アルルの女」のフルート・ソロはつややかで一度、聴いたら忘れることができないと思う。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「ブラームス:交響曲第1番、モーツァルト:交響曲第39番/エーリッヒ・ラインスドルフ指揮 ボストン交響楽団」(BMG JAPAN/TWCL-3013) ラインスドルフは主にアメリカで活躍したせいもあり、ヨーロッパ崇拝主義のわが国では確かに高い人気を持つことはなかった。 ラインスドルフはトスカニーニと同様な指揮者であり、ブラームスの1番は、鋼鉄の固さと、方解石の明快さと、鋭い輪郭と灼熱的な迫力が特徴。基本的にはイン・テンポ(テンポを動かさない)であり、リズムも鋭い。ブラームスやモーツァルトは、ドイツ的ではないと思う人も自分の耳でラインスドルフの演奏を聴いてもらいたい。第1楽章の動機を立体的に積み上げてゆき、それでいて水平の流れのスムーズさも常に保っている。終楽章のコーダの盛り上げ方もこのCDの聴き所。モーツァルトもテンポがきびきびしており、端麗な「第39番」である。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「ショスタコーヴィッチ:交響曲第10番、ハチャトゥリアン:バレエ「ガイーヌ」より/ロリス・チェクナヴォリアン指揮 ナショナル・フィルハーモニー管弦楽団 (BMG JAPAN/TWCL-3014) ショスタコーヴィッチの「第10番」は、ハイティンクやカラヤンの名盤もあり、チェクナヴォリアンのそれもその中の一つに加えてもよい。雄大なスケールでエネルギッシュに表現しており、構成力の確かさと豊かに歌う表情が思いがけないほどの名演を作り出しているからである。特に第2楽章が聴きごたえ充分で、テンポが速く一気に突っ走ってゆくような感じで、精神力の集中した強い運びが魅力的。第4楽章の暗くつぶやくような楽想の提示も美しく、想念の深さと作曲者の音楽語法を完璧に音に示している。「ガイーヌ」はチェクナヴォリアンの名声を一気に高めた全曲盤から4曲収められている。速いテンポでぐいぐいと押し切り、打楽器の効果が凄い。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「シベリウス:交響曲第1番?、ハチャトリアン:交響曲第3番「交響詩曲」?/ロリス・チェクナヴォリアン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団?、レオポルド・ストコフスキー指揮 シカゴ交響楽団? (BMG JAPAN/TWCL-3015) チェクナヴォリアンはアルメニアが生んだ異才の指揮者である。シベリウスは日本未発売の世界初のCD化。チェクナヴォリアンのシベリウスは雄大で、ややはやめのテンポで音楽を追い立ててゆくような迫力とリズムの推進力をもつことが強い印象を残す。シンフォニストのシベリウスに光をあて、特に終楽章を劇的に盛り上げてゆき、壮大なクライマックスを築いてゆく。チェクナヴォリアンは自分の主張を盛り込んでゆくタイプの指揮者である。ハチャトリアンの「交響曲第3番」は15本のトランペット、パイプオルガンを加えた巨大なオーケストラ編成で、アルメニア風の民族的な楽想がこの作品を支配している。(藤村 貴彦 |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「シベリウス:交響曲第4番・第5番/ロリス・チェクナヴォリアン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団」(BMG JAPAN/TWCL-3016) チェクナヴォリアンは、日本ではそれほど知られていないが、彼は1974年にハレ管弦楽団を指揮してイギリス・デビューをはたし、現在は祖国アルメニアのフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督。シベリウスの交響曲第4番・第5番の演奏は北欧的な冷たいシベリウスではなく、第1番と同様に壮大なスケールの裡に、重厚な力感とはげしい緊張と溌刺としたエネルギーが充満している。重厚でマッシーヴな迫力と、輝かしい豊麗さが素晴らしい。特に「第5番」がよく、躍動感があり、生き生きとした音彩が伝わってくる。ロンドン交響楽団を指揮した「トゥオネラの白鳥」は日本未発売。ここでのチェクナヴォリアンは端正で、格調高く表現しており、特に弦の歌わせ方は実に表情豊かである。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「チャイコフスキー:交響曲第6番《悲愴》/レオポルド・ストコフスキー指揮 ロンドン交響楽団」(BMG JAPAN/TWCL-3018) 「悲愴」は名盤も多く、演奏解釈は二通りあると思われる。ロシア的な情念の表出に重きを置く演奏とあくまでも構成を重視する演奏。ストコフスキーの「悲愴」はこの二つを兼ね備えており、テンポの変化は激しくそれが不自然にならず、変化に富んだ豊かな色彩と明澄な美しい音色と、柔軟な妖しい魅力を持ち、楽想は流動的に動く。晩年のストコフスキーが残した貴重な録音。特に第2楽章が美しく、細部の隅々まで丁寧に磨きかけられていて、間のとり方もストコフスキーならではの表情。ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と愛の死は、旋律を充分に歌わせ、ロマンティックな演奏である。ストコフスキーが「音の魔術師」であったことを認識させる一枚。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
「RCAプレシャス・セレクション「R.シュトラウス:交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》?、シベリウス 交響詩《夜の騎行と日の出》?」/ジョルジュ・プレートル指揮 フィルハーモニア管弦楽団?、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団?」(BMG JAPAN/TWCL-3019) フランスの巨匠プレートルは残念ながら、我国では人気が今一つであったが、ヨーロッパではオーケストラの評価が非常に高い。プレートルはフランス音楽で最上の音楽を聴かせるが、R.シュトラウスの作品も得意のレパートリー。「ツァラトゥストラはかく語りき」はベームやカラヤンの名盤もあるが、プレートルのそれは、標題音楽の効果がよく表出されており、有名な「日の出」のトランペットのファンファーレ、ティンパニーの強打は実に劇的である。録音も優秀でこの曲の魅力をあます所なくとらえており、日本で一度も発売されなかったのが不思議である。シベリウスも描写力の優れた名演。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲全集/クラウディオ・アバド指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団」(BMG JAPAN/TWCL-3021~22) アバドが正規に録音した唯一のバッハであり、彼が若き日に自ら音楽監督、常任指揮者を務めて気心の合ったミラノ・スカラ座のメンバーと録音したのがこのアルバム。アバドのひとつの特色である透明・清澄な響きが目立ち、この指揮者のもつ流動感の自然さと、造型の端正さが、美しく整ったバッハを作っている。テンポが少し速めにとられていることもあるが、それがいかにも中庸を得ている感じ。全集の中では特に「第5番」が興味深い。チェンバロ・ソロをピアニストのブルーノ・カニーノが受けもっているからであり、香り高い独特の美しさがある。全体にドイツ風な重々しさはなく、イタリアの明るい太陽を思わせる演奏で、弦の歌わせ方もオペラ的。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「オルフ:カルンナ・ブラーナ/エドゥアルド・マータ指揮」(BMG JAPAN/TWCL-3025) 爆演指揮者として名高いメキシコのエドゥアルド・マータ(1942~1995)がその本領を100%発揮した名盤の復活であり、日本では初のCD化である。マータはメキシコ国立交響楽団やダラス交響楽団の音楽監督として活躍し、RCAから録音も多数。「カルシナ・ブラーナ」はマータの個性がさながらアラベスクのように示され、ダイナミックな迫力と躍動感、音の柔軟な流れとリズムの正確さが両立して、輝かしい成果をあげている。冒頭の「おお、運命の女神」から迫力満点であり、凄い推進力を産み出す。聴きごたえ充分。バーバラ・ヘンドリックス(ソプラノ)、ジョン・エイラー(テノール)、ホーカン・ハーゲコードのソリストも名演を聴かせ、特に第12曲の「昔は湖に住まっていた」のテノールの歌唱が面白い。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「シェーンベルク:月に憑かれたピエロ(英語版)?、ベルク:抒情組曲?/エルガー・ハワース指揮 ナッシュ・アンサンブル?、ジュリアード弦楽四重奏団」?(BMG JAPAN/TWCL-3026) 現代音楽に決定的な影響を与えたシェーンベルクの無調作品「月に憑かれたピエロ」は、20世紀の傑作のひとつにあげられる作品。頽廃と官能美が交差する世界をシェーンベルクは「シュプレッヒシュティンメ」という語りと歌の中間のような語り口で描く。ヴォーカルの女王クレオ・レーンがシェーンベルクの異色作に果敢に挑戦したユニークなアルバムであり、世界初のCD化。この曲の中にひそむ、一種異様な世界が聴き手にせまってくるような表現。現代音楽はまさにこの作品からはじまったような気がする。ベルクの「抒情組曲」は集中度の高い演奏であり、ジュリアード弦楽四重奏団だけに、曲想を深いところでとらえている。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション「鹿の遠音~尺八古典名曲集成/横山勝也」 (BMG JAPAN/ TWCL-3027) 横山勝也といえば、琵琶の鶴田錦史との武満徹の「エクリムス」を始め、オーケストラと共演した「ノヴェンバー・ステップ」の演奏によって名高い。現代邦楽界における尺八奏者の第一人者である。横山は幅広いレパートリーをもつが、彼の本領は尺八古典本曲の中にある。「鹿の遠音」が印象的で、鹿の遠くで啼きあう様子や深山の情景が見事に表現され、二本の尺八によるかけ合いが面白い。西洋の楽器からは決して出てくることがない音である。「鶴の巣籠」は、尺八の特殊奏法を駆使して、鶴の親子の愛情を表現した曲で一度、聴いたら忘れることができないであろう。演奏の良し悪しは邦楽の専門家ではないので記すことができないが、横山は力みのない円熟した表現で全曲を吹いている。学校の鑑賞教材として格好のアルバム。(藤村 貴彦) |
| Classic ALBUM Review | |
 |
RCAプレシャス・セレクション室内楽‘70「三善晃:オマージュ、八村義夫:エリサキ、松村禎三:アプサラスの庭」(BMG JAPAN/TWCL-3028) 室内楽‘70は、野口龍(フルート)、植木三郎(ヴァイオリン)、若杉弘(ピアノ)によって1970年に結成され、現代日本の作曲家に新作を委嘱し、初演を行うことであった。委嘱初演された多くの作品の中から、三曲が選ばれており、三善晃の「オマージュ」は、フルート、ヴァイオリン、ピアノが協調・反発を繰り返しながら緊張感のある音空間を形成してゆく。八村義夫は、47歳の若さで亡くなり、代表作は「錯乱の論理」。タイトルの「エリサキ」とは中世における錬金術で用いられた鉛を金に変える水とのこと。非情な情念がこもった作品である。松村禎三の「アプサラスの庭」は、他の二曲と比べて聴きやすく、オースティナートの音型が不思議な快感を聴き手にもたらせ、響きが美しい。(藤村 貴彦) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「大阪シンフォニカー交響楽団第107回定期演奏会」3月10日 ザ・シンフォニーホール 「ブラームスはふさふさとした髭を生やし、重厚な印象を与える写真が広く知られている。そのせいか、その音楽には深遠な響きが込められ、思索的であると受け止められている。だが、同時に生気溌剌として、弾むような情熱あふれる側面も見落とすことができない。この日、竹澤恭子の演奏した「ヴァイオリン協奏曲」は、まばゆいばかりの輝きを発散させて、魅力的なブラームス像を築いた。ブラームスの持つ独特の渋味は希薄になり、極上のドイツワインのように、まろやかな美味になっている。そこには竹澤の明確な音楽観が刻み込まれていた。これも楽曲に対する深い理解と、冴えた技量に支えられているからであろう。指揮者の大山平一郎も竹澤の音色を生かして、オーケストラをよくまとめていた。ソリストとオケとの一体感は緊密なもので、とりわけ第3楽章のコーダは圧巻といっていい。 「交響曲第4番」は、ブラームスの特色を凝縮したような作品であるが、大山は何のケレン味もなく正攻法で進んだ。滑り出しはやや安定感を欠いたものの、中間楽章あたりからぐっと引き締まり、フィナーレは壮大に盛り上げた。(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「新国立劇場公演《運命の力》」3月15日 新国立劇場オペラ劇場 新国立劇場の3月公演は、2006年に入ってからの初めての新制作で、ヴェルディの大作「運命の力」。ヴェルディ作品のなかでも指折りのスケールの大きさをもつ悲劇である。名作である割に上演の機会が少ないのは、適切な声と表現力を備えた歌手と、スコアの魅力を伝えられる力を持った指揮者を揃えることが困難なせいではないだろうか。今回の上演は、その両方ともに満足の行く水準に達していた。 歌手に関していえば、主要な役3人はいずれも熱唱。とくに出色だったのはレオノーラ役のアンナ・シャフジンスカヤで、艶と深みのある美声が、劇場のすみずみまで行き渡るさまには魂を奪われた。大成が楽しみなドラマティック・ソプラノである。ドン・アルヴァーロ役のロバート・ディーン・スミス、ドン・カルロ役のクリストファー・ロバートソンの好演に加え、グアルディアーノ神父を歌ったユルキ・コルホーネンも、力強い美声で要の役を締めた。歌手陣に気を配りながら、スコアの流麗さ、活力を浮かび上がらせた井上道義の指揮も魅力的だった(オーケストラは東京交響楽団)。 作品の舞台である国、スペイン出身のエミリオ・サージの演出も、納得の行くもの。リヴァス公爵による原作は、「旧社会を代表するドン・カルロと、新しい価値観を備えたドン・アルヴァーロとの対比」をテーマとしていると解釈するサージは、そのアルヴァーロが運命に翻弄されて絶望感にとらわれていくさまを、舞台上に設定した教会(ただしシンプルで抽象的な装置)が次第に小さくなる姿に重ねあわせて表現し、効果をあげていた。20世紀前半に時代を設定した関係で、「スペイン国民軍」のキャンプとされた群衆の場面も、動きが美しくかつ無駄がなく、音楽と一体化しており見事。赤を基調に、紗を多用した舞台も美しかった。 最後に、プログラムについて一言。新国立劇場のプログラムは、毎回幅広い分野の書き手を起用して、作品の背景をさまざまな角度から解説してくれるが、今回はとくに歴史家や神学者によって、「運命の力」の原作が立脚している宗教観、運命観や、当時の社会状況が立体的に読み解かれ、とかく「荒唐無稽」の烙印を押されがちな「運命の力」のストーリーが、実は筋の通ったものであることを教えてくれた。このような編集方針のプログラムが、他の公演でも増えてくれると嬉しいのだが。(加藤 浩子) |
| Classic CONCERT Review | |
 写真:K.Miura |
ロンドン交響楽団演奏会」3月15日 フェスティバルホール 指揮者のチョン・ミョンフンと共に英国の名門オーケストラが来日した。95年以来コリン・デイヴィスの薫陶を受けてきたが、07年からロシアの人気指揮者ヴァレリー・ゲルギエフにバトンタッチされ、新たな門出を迎える。情熱的なバトンで知られるミョンフンは、紳士の国のオケからどんな響きを引き出すか期待をもって会場に足を運んだ。 ウェーバー歌劇「魔弾の射手」序曲は軽快な響きで、重々しさを感じさせないところがよい。オケのまとまりはよく、ホルンが光った。ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」は、ラヴェルの編曲によって、光彩陸離たる管弦楽曲に変身し、ロシア音楽の中でも高い人気を誇っている。親友の画家ハルトマンの展覧会場を訪れたムソルグスキーは、その時の印象を10曲の組曲にまとめた。この中で、圧倒的な音の奔流でフィナーレを迎える第10曲「キエフの門」が鮮烈な印象を残した。オーケストラから骨太な旋律を引き出して、ぐいぐい迫るミョンフンの手腕は見事である。これに対して、第4曲「ビドロ」の物悲しい楽曲では、苦渋する人々の心理のヒダをもっときめ細かに描きたいところだ。 横山幸雄の弾いたショパン「ピアノ協奏曲第1番」は、過度に感傷におぼれることなく、それでいて適度に甘さを残して、爽やかである。最終楽章の仕上げはとりわけ丹念で、一段と力を蓄えてきた。横山はデビューして15年、自分の道をしっかり踏みしめて、若いながらも、完成されつつあると思う。(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「日本フィルハーモニー交響楽団 第578回定期演奏会」 3月16日 サントリーホール 1975年の日フィルの初演以来、数々の名演を繰り広げてきたハンガリーの指揮者、ルカーチ・エルヴィンがバルトークの「青ひげ公の城」を指揮し、大きな成果を上げた。ルカーチはその都度好評を得た熟練者で、彼が指揮すると生気のある音楽を聴かせ、作品の骨組みがしっかりと把握ができ、様式感とぴったりの再現を行う。1928年生まれのルカーチは現在78歳。その指揮姿はかくしゃくとしており、無駄な身ぶりがないのだが、日本フィルはまるで魔法にかけられたかのような美しい音を出し、響きも豊かになる。見事なバルトークであったが、今回の演奏に花をそえたのは、1948年、ブタペストに生まれたバリトンのコヴァーチ・コロシュ。明と暗の境、歌と語りの境、生と死の境を巧みに描ききり、その声の使い方はまさに千変万化。コロシュの歌を聴いていると、彼は青ひげ公を演じるために生まれて来たのではないかと錯覚してしまう。それだけにコロシュは青ひげ公になりきっていたのである。オペラで活躍している渡辺美佐子もユディットの役をよくこなし、最初は声を抑えていたが、少しずつ熱を帯びてゆき、クライマックスに向けて緊張した音楽を築いてゆく。青ひげ公の実演を聴いたのは五度目だがこの作品を理解することができたのは、今回の日本フィルの定期であり、それだけ演奏の内容がよかったのである。ルカーチは作品の成立や初演の経緯に関しての貴重な証言をバルトークから聞いたとの事。バルトークの意図を深く読み取った演奏だったと思う。 プログラムの前半はリストの「ピアノ協奏曲第2番」。独走者の河村尚子は力強い音で正面きって堂々と音楽を押し進めてゆく。テクニックはほぼ完璧。どの楽想も十分な音量で正確に弾いていた。将来が楽しみなピアニストである。(藤村 貴彦) |
| Classic CONCERT Review | |
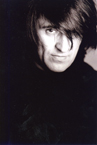 |
「東京フィルハーモニー交響楽団 第719回定期演奏会」3月19日 オーチャードホール ヴィオラ奏者として、我が国でも人気の高いユーリー・バシュメットが東フィルの定期で指揮をし、協奏曲を弾いた。バシュメットの演奏に触発されて作品を書いた作曲家も多く、シュニトケのヴィオラ協奏曲もその一つ。ソリストやオーケストラの団員の中には指揮者になる事を希望している人が多い。オーケストラを指揮する事によって、表現の幅が拡大し、自己の音楽を創造したいからであろうか。ソリストで成功したからといっても、指揮者で成功するかどうかはわからないというのがバシュメットを聴いての感想である。バシュメットの指揮は大変精力的だが、管弦楽を能率的に動かす術を心得るまでには、今一ついっていないようで、テンポが安定せず、少しずつ速くなってしまうのが残念。プログラムの最初はシューベルトの交響曲第4番「悲劇的」。響きは明るく、どの楽章も今まで聴いた指揮者よりもテンポも速く音量も豊かであったが、音楽的意味をもっと作品の内部に入ってつかみだす必要があったように思う。プログラム後半の「悲愴」もそうで、第1楽章第2主題の提示の仕方や第2楽章は、もう少し豊かな表情がほしく、第3楽章もスピード感と力感だけの演奏であった。終楽章はオーケストラを朗々と歌わせ、弦の美しさが印象的。バシュメットの指揮は、ディテールのニュアンスよりも明快さを、重い足取りより速いテンポを好み、旋律も粘るより淡白に進行させるのが特徴のような気がする。 コンサートの中では、ホフマイスターの「ヴィオラ協奏曲」が楽しかった。この作品をコンサートで聴いたのは初めてである。ここではバシュメットが指揮をしヴィオラを独奏。ヴィオラがヴァイオリン、時にはチェロのように響き、音の張りも充分。ヴィオラ奏者としてのバシュメットの真価を心ゆくまで接する事ができた。(藤村 貴彦) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「読売日本交響楽団 第126回東京芸術劇場名曲シリーズ」 3月24日 東京芸術劇場 指揮者の上岡敏之がドイツから読売日響を指揮するために帰国し、久しぶりに彼の音楽を聴く事が出来た。上岡がNHK交響楽団を指揮し、日本でデビューしてから5年の年月が流れたが、更にスケールが大きくなり、成長して来たような感じで、筋の良い音楽が自然に内から流出してくるような、モーツァルトであり、ブラームスの演奏であった。上岡の指揮は、カルロス・クライバーのようであり、まるで舞踊を見ているかのよう。運動神経抜群の指揮で、一歩あやまればオーケストラがバラバラになり、きちんと縦の線をそろえることは難しく、一種即興的な快感を伴う演奏であったが、上岡が指揮するとテンポとリズムがきちんとそろい、気分ののった表現は聴いていて気持ちが良い。上岡は東京芸大でメルツァーに師事し、その後はキール市立歌劇場の練習ピアニストからスタートし、ドイツ系の指揮者と同じような道を歩む。上岡は各地の劇場を経験し、その間に自分の芸術をきたえ、指揮者コンクールに入賞してから、オーケストラを指揮し、シンフォニー・コンサートで脚光を浴びる事はしなかった。上岡の指揮者としての実力は、未熟なうちにスターに押し上げられた場合とは桁違いの豊かさを持っている。上岡敏之の活動から目を離す事ができない。 プログラムの前半は、モーツァルトの交響曲第36番「リンツ」。流れるような指揮であり、オーケストラも慣れないと彼の棒についてくるのは難しかったように思う。後半のブラームスの交響曲第1番は、軽重明暗の造出がしっかりしていて、第2楽章の美しさは格別。楽員が受け身ではなく、積極的に音を出していたのも印象に残り、終楽章のコーダも実に力強い。ドイツで活躍している上岡だが、日本のオーケストラも積極的に指揮してもらいたい。(藤村 貴彦) |
| Classic CONCERT Review | |
 写真:K.Miura |
「東京都交響楽団 東京芸術劇場シリーズ『作曲家の肖像』Vol.59〈チャイコフスキー〉」3月25日 東京芸術劇場 開演前に東京芸術劇場のチケット案内に行き、ポスターを見ると完売と記されており、都響の「作曲家の肖像」は満員の盛況。チャイコフスキーを聴きたいのか、指揮者のオンドレイ・レナルドの人気が高いのかはわからないが、最近の都響のコンサートは聴衆が多い。邦人作品をメインに置いた1月の定期公演もそうであった。楽団員が懸命に良い演奏をめざしている様子が聴衆にも伝わり、そのことによって都響はファンを少しずつ獲得していったのだと思う。オーケストラを取り巻く環境は依然として厳しいのだが、常に前向きな姿勢で音楽に取り組んで行く都響の活動を今後も見守っていきたい。 今回の公演の指揮者は、新星日本交響楽団とスロヴァキア・フィルの首席指揮者、スロヴァキア国立歌劇場の音楽監督を歴任した名匠オンドレイ・レナルド(今年64歳)。レナルドは1978年以来数多く来日し新星日響を主に指揮して好評を博したがレナルドの音楽は少しも神経質にならずたっぷりとし、あふれるように流れる。密度と容量を兼備した指揮者、それがレナルドである。 「スラブ行進曲」はオーケストラの定期ではめったに演奏されない名曲の一つであり、実演で聴いたのは今回が初めて。テンポが実に良く、明解にくぎられていくフレージングが断固とした力を放射した演奏で、金管も日本のオーケストラで聴けないような厚みと光輝を持っていた。 プログラムの後半は「悲愴」。内部に秘められた情熱が演奏が進むにつれて表面ににじみ出るように現われ、特に第3楽章から終楽章に向けて、音楽が加熱してゆく。聴きごたえのある「悲愴」であった。日本のオーケストラからこれほどの「悲愴」を聴いたのは初めてである。(藤村 貴彦) |
| Classic CONCERT Review | |
 写真:三浦 興一 写真:三浦 興一 |
「伊藤恵シューマンの夕べ」3月25日 神戸新聞松方ホール シューマンをライフワークとする伊藤の熱い想いを感じさせるリサイタルである。彼女の手にかかると、シューマンの楽才はかくも豊かであったかと、改めて驚嘆させられる。同じ年に生まれたショパンに比べて、幾分控えめな存在にみられるが、果てしなく広がる肥沃な「ピアノの森」が地平に伸びている。変奏の巧みなことにかけては、シューマンの右に出るものはないであろう。 「アベッグ変奏曲」ではこの題名にちなむ音形(主題)を巧みに生かして、旋律は次々に流転していく。快活な表情に、ちょっと生真面目な素顔ものぞかせて、変奏の面白さを十分に味わった。変奏の集大成が「交響的練習曲」である。詠嘆的な主題が巧みに変容して姿を消し、また戻ってくる。その変幻自在の旋律を伊藤は少し体を揺らしながら弾いてゆく。シンフォニックな深い響きがあり、決して恣意的に流れない。まさに伊藤の目指す境地であろう。時折みせる左手の柔らかな動きには、甘美な世界へ誘う調べが秘められて、豊かな才能の一端をみせている。「ピアノ・ソナタ第3番」はロマン派の色彩にあふれる作品で、ひたすら抒情に身をまかせた音の一つひとつに、磨き抜かれた伊藤の感性在をみた。(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「東京フィルハーモニー交響楽団《マーチ特別演奏会》」3月28日 文京シビックホール大ホール マーチファン待望のオーケストラによるマーチの祭典だつた。最近では一般の吹奏楽団でさえ、正当なマーチを演奏することが少なくなっているので、原曲のオーケストラによる演奏には期待されていた。指揮は金聖響により「ロサンゼルス・オリンピックファンファーレとテーマ」、スツペの「軽騎兵序曲」などが軽快に演奏された。次いで160人もいる東フィル奏者の内、管打だけの独自メンバーと、サキソフォーンパートとして賛助出演に「トルペール・クワルテット」を迎え、にわかに吹奏楽の編成に衣替えして、「ブロックM」やスーザの「雷神」などを原曲どおりに演奏した。やや指定のテンボより早い感じだったが鑑賞用としては上出来だった。後半は懐かしい「スポーツ行進曲」などを披露した。ゲストの音楽評論家玉木正之が「東京オリンピック・マーチ」を指揮した。最後にレスピーギの交響詩「ローマの松」がバンダも加え華麗に演奏された。(斎藤 好司) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
「いずみシンフォニエッタ大阪第12回定期演奏会」3月30日 いずみホール 腹話術師のいっこく堂が人形とともに、ストラヴィンスキーの音楽劇「兵士の物語」に挑戦し、意表を突く舞台づくりに成功した。常任指揮者の飯森範親もシンフォニエッタを巧みにコントロールして、ファンタジックな世界をソフトなタッチで描いた。 ロシアの兵士が帰郷の途中で悪魔に出会い、愛用するヴァイオリンと魔法の本を交換し、富を得るが、最後はどんでん返しという物語である。兵士、悪魔、老人の姿をした3つの人形が主役で、これに語り手も加えて、いっこく堂は1人4役の奮闘振りである。人形はユーモラスな表情で、悪魔もどこか愛嬌がある。舞台に置かれたテーブルをカーテンに見立て、人形の出入りや物語の進行に活用した。人形の動きにどこか劇画を思わせるところがあり、腹話ながらも声がよく通った。いっこく堂の芸の冴えというべきであろう。 音楽は、第1部では、軽快な行進曲によって、兵士が大金持ちになっていく様子が生き生きと表現される。第2部では、悪魔と兵士の争いが、ジャズやタンゴのリズムを交えながら波乱を巻き起こす。情景の変化に合わせてメリハリをきかせた飯森の指揮は、ストラヴィンスキー音楽の躍動感をよく伝えていた。(椨 泰幸) |
| Classic CONCERT Review | |
 |
フレディ・ケンプ・ピアノ・リサイタル」4月2日 ザ・シンフォニーホール 往年の巨匠ウィルヘルム・ケンプの遠縁という育ちのよさに加えて29歳の若さで、溌剌とした印象である。ダイナミックな奏法でテンポは速く、力強いタッチは最近の若手ピアニストによくみられる傾向である。これを繊細さに欠けるとみるか、爽快と評するか見方の分かれるところだが、自らの新しい音楽性を創造していく途上にあるとみたい。 ベートーヴェンのピアノ・ソナタをそろえて臨んだが、ケンプらしさがあるとすれば、第23番熱情に尽きるだろう。第1楽章のいわゆる「運命の動機」から異様なまでの迫力があり、最終楽章まで息も継がせずに、ひた押しに押してくる。熱情とは爆発であると信じて、破壊的なエネルギーを発散させる。この人の身上であろう。ところが、一転して第14番月光になると、この突進力を持て余しているらしく、最弱音の連続に耐え切れなくなって、破綻しそうになる。極上の練り絹のような淡い光沢と、深々とした漆黒の闇の静けさをいかに描き分けるか。今後の課題であろう。最後に演奏した第29番ハンマークラヴィアは抑制の利いた奏法であったと思う。(椨 泰幸) |
| Classic INFORMATION | |
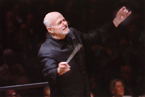 |
「チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団withヨーヨー・マ」6月3日午後3時 ザ・シンフォニーホール スイスの名門チューリッヒ・トーンハレが、首席指揮者のデイヴィッド・ジンマンと共に来日し、大阪でドヴォルザーク「チェロ協奏曲」、シューマン「交響曲第2番」を演奏する。ジンマンはニューヨーク出身で95年から同管弦楽団の首席を務め、オーケストラの演奏能力を向上させた。ヨーヨー・マはパリに生まれ、ニューヨークでチェロを学び、世界的奏者として活躍中。お問い合わせはザ・シンフォニーホール(06-6453-6000)へ。(T) 〈写真:Priska Ketterer, Tonhalle Orchestra Zurich〉 |
| Classic INFORMATION | |
 |
「大植英次指揮ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー」6月4日午後3時 ザ・シンフォニーホール 大植が88年から首席指揮者を務めるハノーファーを率いて、地元大阪に凱旋公演する。曲目はワーグナー作品ばかりで、歌劇「リエンツィ」序曲、ジークフリート牧歌、楽劇「ワルキューレ」第1幕(演奏会形式)で、ワーグナー歌手として著名なロバート・ディーン・スミス(テノール)やリオバ・ブラウン(ソプラノ)らも登場する。 大植は03年から大阪フィルハーモニー交響楽団の音楽監督を務め、05年には東洋人として初めてワーグナー歌劇の総本山バイロイトに登場し、「トリスタンとイゾルデ」を指揮して話題となった。お問い合わせはザ・シンフォニーホールへ。(T)〈写真:Ann Marsden〉 |
| Classic INFORMATION | |
 |
「ボローニャ歌劇場びわ湖ホール公演《イル・トロヴァトーレ》」6月17日午後3時、「《アンドレア・シェニエ》」6月18日 午後3時 ヴェルディの傑作オペラ「イル・トロヴァトーレ」は、スペインの伯爵家を舞台に、数奇な運命に巻き込まれる兄弟の物語で、恋が絡んで悲劇的な結末を迎える。題名役のトロヴァトーレ(吟遊詩人)には人気テノールのロベルト・アラーニャが起用され、相手役の女官にはイタリアを代表するソプラノのダニエラ・デッシーがあたる。ジョルダーノのオペラ「アンドレア・シェニエ」はフランス革命期の波乱に満ちたドラマである。題名役には今人気絶頂のテノール、ホセ・クーラが登場、シェニエを愛する伯爵令嬢はウクライナ出身のソプラノ、マリア・グレギーナが出演する。主役は強靭で輝かしい声を必要とする典型的なドラマチック・テノール、ドラマチック・ソプラノで、オペラでも極めて難役とされる。往年の名歌手マリオ・デル・モナコの子息であるジャンカルロ・デル・モナコが演出、装置、衣装を手掛けるのも面白い。二つのオペラの指揮はカルロ・リッツィで、ボローニャ歌劇場管弦楽団、同合唱団も出演する。お問い合わせはびわ湖ホール(077-523-7136)へ。(T)〈写真:Primo Gnani〉 |
| Audio WHAT'S NEW | |
 |
「アコースティック・マスターピース AM-201(\231,000/税込み) (発売:A&M http://www.hinoetp.com/aandm.htm) A&Mは、日本はもとより米国で大変著名なわが国の管球アンプ・メーカーである。このモデルはプリメイン・アンプで、趣味性の高い管球式としては比較的手頃な価格だ。ややレトロな味わいを漂わせるデザインに懐かしさを覚えるユーザーも多いだろうが、音は非常に現代的で緻密な再現力に富んでいる。作りもしっかりして完成度の高さを十分に備え、また仕上げも堅牢で美しい。音楽ファンにも強くお勧めしたい製品である。(井上 千岳) |
| Audio WHAT'S NEW | |
|
|
「オーディオ・アナログ ENIGMA」(\239,400/税込み) (取り扱い:ナスペック http://www.naspec.co.jp) イタリアの高級アンプ・メーカーとして人気の高いオーディオ・アナログ社の面白い製品だ。CDとチューナー、アンプまで一体となったモデルで、これ一台で全て賄える。あとはスピーカーをつなぐだけで、簡単シンプルなシステムが完成する仕組みだ。しかもアンプ部に真空管を使った珍しい構成。かといって音は決してレトロなものではなく、高解像度である種の熱気も感じさせる。ちょっと高級なエントリー・モデルである。(井上 千岳) |
| Audio WHAT'S NEW | |
 |
「マランツ SA8001」(¥94,500/税込み) (発売:マランツ・コンシューマー・マーケティング http://www.marantz.jp) ハイエンド・オーディオやホームシアターで知られるマランツのハイ℃/PなSACD/CDプレーヤーである。上級機の技術をふんだんに取り入れた贅沢な設計で、普及クラスとしては異例といえるほどの高度な音質を実現している。どんなジャンルの音楽でも不安なく聴くことができ、上級クラスのユーザーが使っても大きな不満は残らないだろう。その意味で大変お買い得なモデルということもできる。(井上 千岳) |